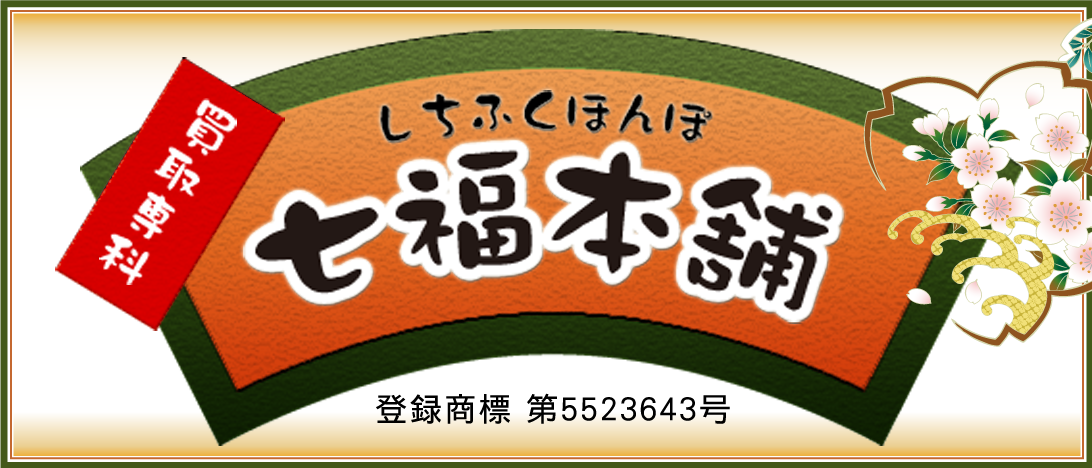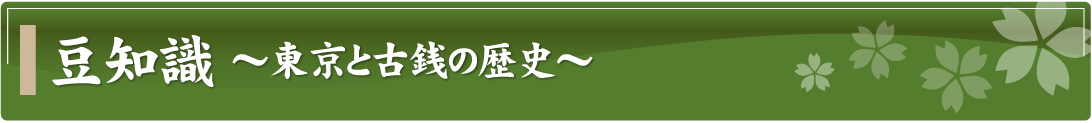東京と古銭の歴史
東京と古銭は深い関係があります。
たとえば銀座は江戸時代には銀貨を作っていたところですし、また、時代劇によく出てくる金色の小判を作る場所(金座)もありました。そして、銅貨を作る場所も。

東京と古銭の深い関係
東京・銀座といえば国内外の一流ブランドが集まるファッションの発信地であり、一方では食の名店・老舗が並ぶ食文化の中心的存在です。また、「銀座のバー」に代表される社交の場でもあり、さまざま顔を持っています。
その銀座2丁目に「銀座発祥の地」の碑があることをご存知でしょうか。
この「銀座」とは、江戸時代に設置された「銀座役所」をさしています。役所といっても銀貨(丁銀、豆板銀など)を作り、管理するところです。
つまり、銀座は古銭ファンに人気がある江戸時代の銀貨を作っていた場所で、そのことから「銀座」という町の名になったのです。
はじめは「新両替町」とされたそうですが、通称はやはり「銀座」で、明治2年になって正式に銀座という町名になりました。

江戸時代の基本通貨は、金貨、銀貨、銭貨の3種類です。
三貨制度と呼ばれますが、「銀座」があるのなら「金座」もありそうですね。
たしかに「金座」もありました。小判のような金貨をつくるところです。
この「金座」の跡地に建っているのが、東京日本橋にある日本銀行本店です。
では、金・銀・銭の「銭」はどうでしょう。
「銭」は、金貨や銀貨に対して使われるもので、多くは銅貨をさします。
しかし、この銅貨はなかなか作られず三代将軍家光の時になって作られるようになりました。
それが、寛永通宝です。そう、あの銭形平次の投げ銭に使われたものです。
そして、「銭座」も江東区亀戸に「亀戸銭座跡」のモニュメントがありますし、墨田区小梅には「小梅銭座跡碑」が建っています。
こうしてみると東京と古銭の関係は深いですね。
古銭を売りたい、あるいは買取ってもらいたい、古銭ファンの皆さんはコレクション充実のためいろいろとお考えのことと思います。
お時間があれば銀座2丁目の「銀座発祥の地」の碑をはじめ、東京に残る古銭と深い関係がある場所を散策するのも楽しいのではないでしょうか。これも古銭ファンならではの楽しみと言えそうです。
江戸時代の貨幣はもちろん、国内の記念硬貨・記念コイン・金貨をはじめ、売りたい方や買い取りのご相談をしたい方、高価買取のことならお気軽にお問い合わせ下さい。
関連記事
買取品目一覧
買取専科 七福本舗