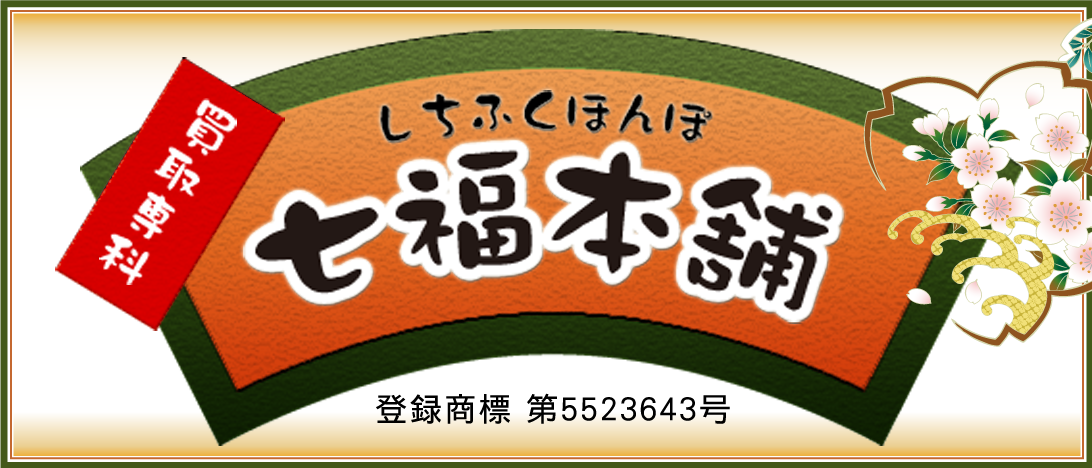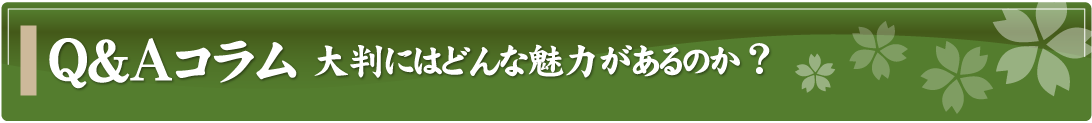大判にはどんな魅力があるのか?
大判金貨の始まりは豊臣時代で、本格的な大判の鋳造は江戸時代に入ってからです。江戸時代、縦約14センチ強、幅8センチ、重量160gもある大きな金貨幣「慶長大判」、「天保大判」が鋳造されました。
これら大判の鋳造枚数は極端に少なく、歴史的古銭としての価値と相まってその希少性の高さが魅力です。

大判の希少的な価値とは?
古代から現代に至るまで金は、世界中で特別な価値を持つものとして考えられ、取り扱われてきました。
日本においても例外ではなく、歴史上に登場する様々な「大判」という金貨がそれを物語っています。
そこで興味があるのが、当時流通した大判が「現在はどれほどの価値・魅力があるのか?」という点です。
まず実際に使われていた大判の情報とともに、戦国時代から現代にいたるまで、日本の金は、どのように扱われてきたのでしょうか。
大判とは、金の塊を槌で叩いたり、伸ばしたりして作られた、薄く大きく広げた楕円形の貨幣のことです。
大判の種類には、桃山時代から江戸時代にかけて11種類ありますが、その代表的なものは「天保大判」と「慶長大判」です。
天保9年(1838年)から万延元年(1860年)の間に鋳造された「大判」に「天保大判」があります。
大判の大きさは、縦143ミリ、幅84ミリ、重さ約165g、となっています。
1838年から1860年の約22年間でわずか1,887枚のみの鋳造なっており、その高い希少性から古銭金貨市場においては100万円以上の値段で買取りがされています。
実際に手にしてみると、その大きさ、重量から非常に魅力的な金貨だということがわかります。
一方、「慶長大判」は、慶長6年(1601年)から鋳造された大判で、「慶長笹書大判金」、「明和大判」と呼ばれる明和暦(明和01-09年、1765年-1772年)に鋳造されたものなどの8種類ほどに分類されますが、重量は164.9グラムとなっています。
「慶長大判」は「天保大判」よりその価値は非常に高く、「慶長笹書大判金」は古銭の買取市場では、1枚2,500万円から4,500万円の非常な高値で取引されているほどです。
また「天正菱大判金」(天正16(1588年)~天正19(1591年)も、金純度や希少価値の高さは群を抜いており、5枚のみが現存すると考えられてきました。2015年にスイスのオークションに登場し、1億4300万円で落札されました。

金は実物自体に価値があり、「イザというときの金」とも言われ、無価値になることはありません。
株式や債券とは異なる値動きをする資産運用の対象として重宝されています。
特に大判は、現存する枚数が少なく、保存状態が良いものほど高値で取引されています。安いものでも数百万円、人気があり、さらに大判の種類や状態が良いものであれば数千万円で取引されるケースも珍しくありません。
現在の大判は、単に「金」としての資産価値だけでなく、その古銭としての歴史的価値・希少価値も一緒に判断されます。
記念硬貨・記念コイン・金貨をはじめ、売りたい方や買い取りのご相談をしたい方、高価買取のことならお気軽にお問い合わせ下さい。
関連記事
買取品目一覧
買取専科 七福本舗