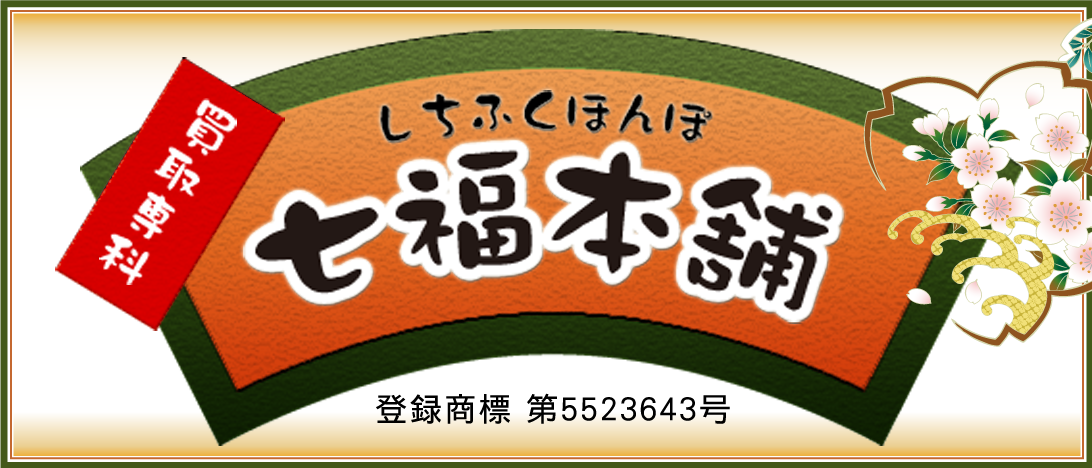小判はよく売買されている?
小判は江戸時代に鋳造され、流通した貨幣です。小判の種類は全部で10種類あります。
代表的な小判としては「慶長小判 」、「享保小判」、「天保小判」、「万延小判」などがあり、種類によって小判の品位や現存数が違うものの、多くの小判が売買されています。

売買市場でも人気の小判
日本国内で、江戸時代に流通していた通貨のひとつに「小判」があります。
楕円型をした米俵のような見た目で、素材に金が使われています。
江戸時代の小判には、「慶長小判」(慶長6年・1601年)頃、「元禄小判」(元禄8年・1695年)、「宝永小判」(宝永7年・1710年)、「正徳小判」(正徳4年・1714年)、「享保小判」(正徳4年・1714年)、「元文小判」(元文元年・736年)、「文政小判」(文政2年・1819年)など10種類ほどあります。
これらの小判は、どれも金を原料とした貨幣のため、高値で買取りされています。また、現存枚数が少ないことも、小判が高い価格で取引されている要因でもあります。
小判の価値判断のポイントは、「骨董価値・希少性の高さ」にあります。
骨董品の収集家は、日本だけでなく海外にも大勢います。コレクターやマニアに需要があるため、骨董品としての価値が高い小判は、高価買取での売買が期待できます。
その骨董価値の高い小判として、「元禄小判」が挙げられます。
「元禄小判」は、1695年から流通が始まった小判ですが、慶長小判よりも大幅に金の品位を下げ(慶長小判の金の含有量15gに対し、元禄小判の金の含有量は9.75g)たため、価値のある貨幣ではありませんでした。
しかし現存する数が少なく、ほとんど市場に出回らないため、「元禄小判」を渇望する古銭収集家も少なくありません。
一方、現在でも買取市場で売買される小判は多くあり、代表的な小判としては、「慶長小判 」、「享保小判」、「天保小判」、「万延小判」などがあります。
例えば、天保小判は天保8年(1837年)に鋳造・流通が始まりましたが、その発行枚数は江戸時代の他の小判の発行枚数と比べても圧倒的な枚数で、800万枚以上といわれています。
しかし、現在の市場に出回る数は少なく、小判としての価値は希少です。
また、収集用アイテムとしても人気が高いため、レプリカも多く出回っており、本物かどうかを見分けるのは極めて困難ともいわれています。

小判のアンティークコインとしての価値はどうでしょうか。
アンティークコインとしての価値の要素には、「歴史の古さ」、「現存数の多寡」、「金の含有量」、「デザインの人気度」、「その他」があげられます。
その面からも小判には、大変な価値が認められます。
記念硬貨・記念コイン・金貨をはじめ、売りたい方や買い取りのご相談をしたい方、高価買取のことならお気軽にお問い合わせ下さい。
買取品目一覧
買取専科 七福本舗